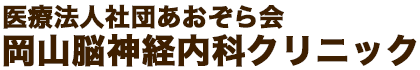2025/11/01
パスカルの名言、「人間は考える葦である」由来です。フランスの哲学者であり、数学者であり、物理学者であり、実業家でもある天才。人間は弱い存在ながら「考える」ことが出来る点で他の存在に長じることを説いています。最低でも4刀流の偉人の言葉です。せっかくの能力、しっかり使いなさいよと言っているのかも知れません。考える力の成果の代表はノーベル賞。つい先日発表があり、ノーベル生理学・医学賞、ノーベル化学賞の2部門で日本人が受賞する快挙となりました。過去を含めた国別受賞数は米国、英国、ドイツ、フランス、日本と続き、第5位です。自分がもらったわけではなくとも皆の自信につながります。
受賞者の出身大学をみると、京都大、名古屋大、東京大、東京工大(現東京科学大)、北海道大、東北大、九州大と続きます。お受験偏差値No.1の東大ではないですねえ。京大は東大よりも自由でのびのびした環境が準備されている印象ですが、実際はどうなのか?受賞者は、お受験に強い私立校出身者よりも地方の公立校出身者が多いことも指摘されていますね。受験を目指して一心に勉強に励むところと、異なる目的を持つ若者が集まり、様々に夢を語り合うところ。どちらが脳の可塑性を伸ばせるか。良い研究成果を得るためには研究環境、支援体制、興味ある研究に集中できる自由度等の重要性が指摘されています。お受験では主に知識量が評価されますが、研究成果には発想や粘り、執念が大切と感じます。この時代、単なる知識はAIが教えてくれるので、大切なのは「考える力」、すなわち発想や企画力かな。それを検討するために方法論を教えてくれる指 導者の懐の広さ、設備、資金も大切そうです。
受験勉強、特に子供の頃のお受験勉強は、様々な体験をもとに脳を発達させるべき時代にレールに従って知識を教え込むので、安全ではありますが、反って能力の発展を邪魔するのではないかとさえ思えます。私事、田舎の自由のびのび小学校から、進学熱の高い町の中学校に上がった時に感じた違和感。小中学生時代は、野山を駆け、流れる川面や雲を眺め、鳥や虫の声を聴き、魚を追い、四季の変化を楽しむ日々。雨の日は読書。神経科学をかじった今思うと、多種の刺激が神経のネットワークをより伸ばすかも。基本的な世界の流れ、歴史や地理や古典などの知識は教養として大切ですが、細かい記憶は今やAIに任せておけば十分なのでは。入力すれば、瞬時に回答が出るでしょう。若者には、お受験の延長でクイズ王になるよりも、好奇心、探求心を持って解答のない真理の究明に挑戦して欲しいです。最後まで結果が出ない場合は何も形に残りませんが、神経回路の発達とともに、挑戦自体が人生の糧となるでしょう。その過程で人的ネットワークが増えるのも財産。
同じことがスポーツ界でもありそう。大成した方は、子供のことから一種目だけでなく、いろいろな活動に励んでいたりします。やり投げの北口選手とか。MLBで活躍目覚ましい日本人選手の皆々も意外と甲子園常連校出身ではなかったりします。
発展途上の頭、身体は多様な刺激によって、より効果的に伸びるのではないかと思う次第です。